
お夏の葬儀から家に帰る途中のバスで、僕は彼女がいつか話した二匹の針鼠の物語が脳裏に浮かんでいた。
雪と氷に閉ざされた森に二匹の針鼠。
外は寒く、いつ凍え死にするかわからない。二匹の針鼠は互いに相手のことを心配して、自分の体温で相手に暖かさを渡したがる…。
しかし残念ながら体は棘だらけ。相手を抱きしめたとたんに、鋭い棘が相手を傷付ける。
痛いと感じると、相手から離れ、でもまた相手を抱きしめたい。
抱きしめ、傷付け、離れ、抱きしめ、傷付け、離れ。
だが、当時の僕はこの物語が納得いかなかった。
「おいおい、これが物語だと言えるものか。結末もないなんて」
「どうして? 何の物語でも結末が必要なの?」
そう言いながら、お夏は視線を落とした。
「かといって…」
「私のことが好き?」
ついに彼女は僕にはっきりと聞いた。だが、彼女は相変わらず足元をみつめたままだった。
「はっ、はい…」
「そう。好きだったら、必ず私を傷付けるわね」
「いや、あり得ない! お夏を決して傷付けないよ」
「きっと傷付ける」
「まさか、そんなこと…」
「きっとよ」
彼女は振り返って僕をじっと見つめた。
その確信を得た目付きは僕に弁解することを放棄させた。
「そして…」。彼女は続けた。
「私も同じ。好き。好きだから、君を傷付ける。お互いに深く愛する2人は、お互いに相手を傷付ける…。
2匹の針鼠みたいにね。これは愛というゲームのルールよ。誰も違反するわけにはいかない…」
「何を言ってるんだよ。愛しているから、相手に幸せをさせるべきじゃないのか。なぜ傷付けようとするんだ」
「君はあの二匹の針鼠が不幸だと思っているのかしら……。では、選ぶのはどちら?
? 寂しく凍え死にするのか、しっかり抱きしめたまま相手の棘に刺し殺されるか」
「あの……」
僕が答えられないのを予想したように彼女は話す。
「私は、お互いに抱きしめたほうがより幸せだと思うわ。痛いけど、その傷口は愛されている跡でしょ」
その後で彼女がまた何を話したか、もう覚えていない。
だが、その予言は不幸的に当たってしまった。
確かにあれからの7年間に、僕ら2人はル―ルにしたがって、絶えず相手を傷付けてきたのだ。
より怖いことは、お互いに苦しみをもたらすのがはっきり分かっていたくせに、なんとこの惨いゲ―ムを終わらせるつもりが少しもなかったことだ…。
「浮橋駅に着きました。押さないでください」
バスのアナウンスが僕を思い出の中から呼び戻した。
バスを降りて、僕は一生懸命に家の方へ走る。
それらの思い出を全部遠く残したままにしたいから。
作者:ちょうてつ
~上海ジャピオン6月5日号より




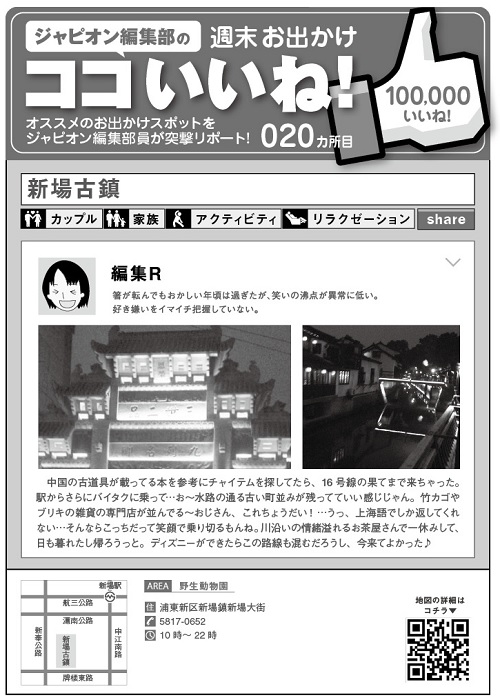











 PAGE TOP
PAGE TOP