
「やはり珊瑚はとても美しい。
ただし、その美しさの下にどれくらいの屍が積もっているのかなあ」
今日まで、私はずっとこの言葉を忘れられない。
友達のお虫が死んでいくとき、この話を何度もぼそぼそとしていたのだ。
あっ、自己紹介を忘れちゃった。
ごめん。まず、紹介させていただきたい。
私は一匹の海老だ。生まれたばかりの頃からこの水族館に暮らしてきた。
この水族館には何千種類もの生物が生活していて、皆毎日厚いガラスを通して、自分の姿を展示したり観光に来るお客さんを楽しませたりしてきた。
その中でも一番美しく、人気があるのは珊瑚夫人であろう。
その色鮮やかで立派な姿を見ると、誰でもその美しさに感心するに違いない。
私のような下衆なヤツにはそんな立派なお方と付き合う機会がないのは当たり前のことだ。
しかし、私より卑しいヤツはまだいるぞ。
お虫こそ、そんな可哀想なヤツである。
お虫と彼の家族は珊瑚虫として自らの短い命のすべてを珊瑚夫人に差し上げた。
死んだあとも、数えられないほどの珊瑚虫の屍が夫人の足元にもくもくと積もっていって夫人の身体をどんどん大きく、そして美しくしていった。
そんなふうに年々、代々…。
なんでお虫と仲良しになったのか。
たぶん必然的なことだろう。
私は若いのに、二本の長い髭と猫背ゆえに時々つまらないやつらに嘲笑われたりした。
笑ったことが一度もないのはお虫しかいない。同病相憐れむ、というべきか、彼と喋るのが好きだ。
けれど、お虫はいつもしょんぼりと言っていた。
「君の髭は長いけど、私は必ず君より早く亡くなるわけだね」
しばらく経ったある静かな夜にお虫は死んだ。
私のほかに、誰も彼の死に気付かないらしい。
彼は先輩らと同じように夫人の足元に積もって、美しい身体の一部になってしまった。
しかし、誰も気にしない。
翌朝、水族館は相変わらず賑わっていた。
珊瑚夫人は日頃と同じように自らの美しさを思い切り誇示し、観光客たちも日頃と同じように夫人の美しさを一斉に誉めた。
誰もお虫の死を気にしない。
「…その美しさの下にどれくらいの屍が積もっているかなあ」
お虫が死んでいくときの話を再び思い出した。
「残念ながら、人々はただその美しさに注目してその美しさの代価は何か、少しも関心がないようだ。
惨い美しさと言うべきか、それとも美しい惨さというべきか。
私は人間の世界へ行ったことはない。
でも、観光客の満足した、そして羨ましげな表情から見ると、2つの世界は水族館の厚いガラスで仕切られてはいるが、この点においてはたいてい同じなのだろう」
お虫の後輩どもを見ながら、私は呟いている。
作者:ちょうてつ
~上海ジャピオン4月10日発行号より


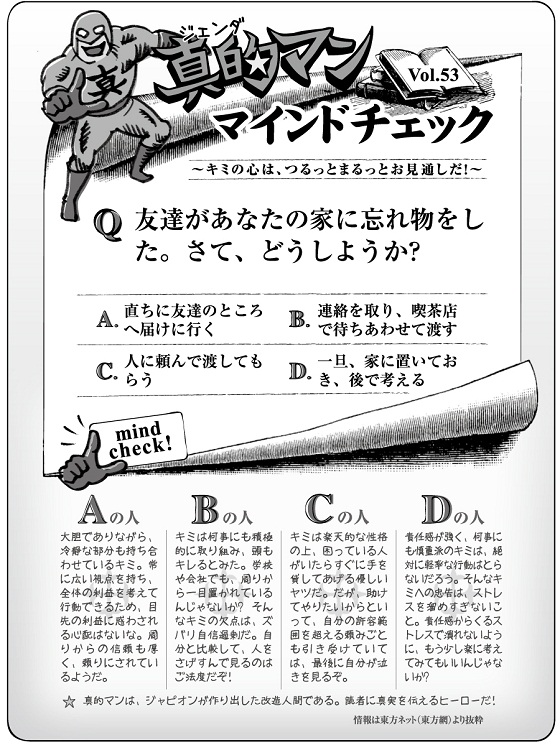
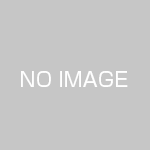












 PAGE TOP
PAGE TOP