脳で感じる不思議な味
 人はどのようにして味覚を感じるのか? 料理人だったら、自然と興味が引かれるテーマだ。1994年。ニューヨークで板前修業を終えた自分へのご褒美として、1カ月間のヨーロッパ・地中海食べ歩きの旅に出た。そして、その旅を通して、ぼくなりにそのテーマに関するひとつの答えを導き出した。ピラミッドとサラダ。その2つが、キーポイントになった。
人はどのようにして味覚を感じるのか? 料理人だったら、自然と興味が引かれるテーマだ。1994年。ニューヨークで板前修業を終えた自分へのご褒美として、1カ月間のヨーロッパ・地中海食べ歩きの旅に出た。そして、その旅を通して、ぼくなりにそのテーマに関するひとつの答えを導き出した。ピラミッドとサラダ。その2つが、キーポイントになった。
旅の目的は、たしか世界各国の料理を食べて、料理人としての幅を広げることだった。出発前には、「ピラミッドパワーで塩が旨くなる。さらに、その塩で料理をすると、すごく美味しい料理ができ上がる」、そんな噂も、ニューヨークの料理人仲間から聞いていた。そこで、せっかくなら確かめたいという思いもあり、旅はエジプトから進めることにした。ついでにピラミッドパワーで、料理の腕もアップするかもしれない、と考えていた。
 エジプトは、気温40度。ペットボトルの水もお湯になるくらい暑かった。そんな中、市内観光も後回しに、まずは一目さんに、ピラミッドへ向かった。階段を登り、中央部の小部屋へ入り、ニューヨークで買って、こっそり旅行カバンに詰め込んだ一番安い塩を取り出して、これでもかとばかりに、ピラミッドパワーを塩に注入してみた。
エジプトは、気温40度。ペットボトルの水もお湯になるくらい暑かった。そんな中、市内観光も後回しに、まずは一目さんに、ピラミッドへ向かった。階段を登り、中央部の小部屋へ入り、ニューヨークで買って、こっそり旅行カバンに詰め込んだ一番安い塩を取り出して、これでもかとばかりに、ピラミッドパワーを塩に注入してみた。
ホテルに戻ると、すぐに、市場で買った肉を、ピラミッドパワーのたっぷり詰まった塩をかけて焼いた。未知との遭遇と期待を膨らませながら、まずは一口。「うん、旨い!」。それもそのはず、あまりの暑さで昼間から何も口にせず、水ばかり飲んで腹ペコ状態だったのだ。このときは結局、どんな塩を使った料理でも、あの状態だと美味しいのではという疑問が、ふと頭をよぎった。
次の日からは、本来の目的であるエジプト料理に挑戦した。「シャコリ」は、米にマカロニやスパゲティーを混ぜ、上からチリトマトソースをかけるという、なんともヘンテコな料理だが、これが意外とイケた。神戸のそば飯もここから発想を得ているのでは? なんて思うほどだ。ほかにも、挽き肉と米をピーマンに詰め込んだ「マフシー」などを食べた。エジプト滞在の4日間で、日本で見たことのあるような料理に結構、出会うことができた。
ピラミッドパワーをとりあえず体験したあとは、陸路を選び、イスラエルを通って塩分の強い死海に行き、エーゲ海へ出た。そこは独り旅のよさ。着の身着のまま、旨い料理があればいい、なんて具合だった、と思う。
ギリシャに着くと、ニューヨークを出てから8日間、これまで、一度も生の野菜を食べていなかったことに気づいた。大の肉好きのぼくだが、さすがにこの時ばかりは、サラダが恋しかったのを覚えている。
ギリシャでは食堂のことを〝タベルナ〟というのだけれど、早速、そこに駆け込んで、グリークサラダを注文して食べた。フェタ(山羊のチーズ)とオリーブ、そして新鮮な野菜を盛った、一見普通のサラダ。これが、本当にびっくりするぐらい旨かった! 日本に帰ったあと、同じ材料で同じサラダを作ろうと思って試したが、今でもあの味は再現できていない。
 話を最初の問いに戻すと、〝人間の味覚は舌で味わう前に脳で感じる〟のではないかと、ぼくは思う。いい例が今回のグリーンサラダだった。8日間、生の野菜を食べられない環境の中で、突然、目の前に出されたそれは、これまでに食べたどんな料理の中でも郡を抜いた旨さだった。脳がこの食べ物は衛生的であると確認した瞬間に、食欲の安全ロックのようなものを解除してゴーサインを出す。そうして初めて、舌は美味しさを味わうのではないか。ピラミッドの塩もそうだ。塩が旨くなるという話を聞いて、半信半疑ながら噂話を信じた。一生懸命準備もしたし、あの時は腹もへっていた。
話を最初の問いに戻すと、〝人間の味覚は舌で味わう前に脳で感じる〟のではないかと、ぼくは思う。いい例が今回のグリーンサラダだった。8日間、生の野菜を食べられない環境の中で、突然、目の前に出されたそれは、これまでに食べたどんな料理の中でも郡を抜いた旨さだった。脳がこの食べ物は衛生的であると確認した瞬間に、食欲の安全ロックのようなものを解除してゴーサインを出す。そうして初めて、舌は美味しさを味わうのではないか。ピラミッドの塩もそうだ。塩が旨くなるという話を聞いて、半信半疑ながら噂話を信じた。一生懸命準備もしたし、あの時は腹もへっていた。
飽食の日本にいると忘れがちだが、どんな状況で料理を食べるかが、本当は一番大切なことなのかもしれない。ぼくにとって旅とは、そんなふうにフィールドワークを通じて食に関する不思議を解明するひとつの手段でもある。
中辻利宏
1969年生まれ、大阪出身。高校卒業後、オーストラリアやニューヨークの日本料理店で修行。その後、日本に戻り大坂全日空ホテルや鹿児島ホテル京セラで日本料理店で腕を振舞う。ウェブサイト「ぐるなびレシピ」の初代クリック数No.1シェフ。現在、創作料理店「にんにん」の総料理長を務める。
宿のお母さんと花嫁たちへ
 入籍して1カ月目のある日。友人が夏休みにトルコ~グルジアをまわらない? と電話をしてきた。2002年当時、旧ロシア領のグルジアではチェチェン紛争の火種もくすぶっていたのだが、私は心配する主人を残し、女ふたりの旅行に飛び出した。
入籍して1カ月目のある日。友人が夏休みにトルコ~グルジアをまわらない? と電話をしてきた。2002年当時、旧ロシア領のグルジアではチェチェン紛争の火種もくすぶっていたのだが、私は心配する主人を残し、女ふたりの旅行に飛び出した。
主人とは、両親の強い反対を押し切って日本で入籍した。式も挙げない寂しい結婚だった。主人を置いて旅に出たのは、そんな新婚生活に慣れずにいたせいかも知れない。そうして出かけた旅先での、ふたつの偶然の出会いを、私は今でもはっきりと思い出す。
グルジアでは、旅行者を受け入れてくれる民家に泊まった。スターリンの故郷であるこの街は、建造物の何もかもが美しかった。
丘から街を見下ろしていると、教会で式を挙げた家族が記念写真を撮っている。東洋人が珍しいらしく、そこで記念撮影に誘われた。そんな瞬間に立ち会えた偶然に、私も友人も笑顔を隠し切れず、祝いのワインを全員で飲み干した。ふと、私と主人も、結婚記念の写真くらい撮っておけばよかったなと思った。
 その後私たちは、バスでトルコへ入り、サフランの産地として有名なサフランボルへ移動した。バスに乗り合わせたトルコ人は、日本の京都のような古都だと教えてくれた。
その後私たちは、バスでトルコへ入り、サフランの産地として有名なサフランボルへ移動した。バスに乗り合わせたトルコ人は、日本の京都のような古都だと教えてくれた。
宿泊先は「バストンズペンション」という民宿。そこは、夫婦とその家族が切り盛りするアットホームな宿だった。宿泊費に2ドル追加で、宿のアンネ(お母さんの意)お手製の朝食と夕食が付いた。
アンネは、大きな話し声と笑顔が素敵なひとだった。宿が連日満員なのは、彼女の人柄のせいだとすぐ分かった。部屋がなかったので、初日はリビングで雑魚寝になってしまったが、友人も同じ気持ちだったようで、部屋が空くまで気にしないと笑っていた。夕飯を手伝ったり、朝食のジャムのためにベリーのヘタを取る手伝いをしたり……そこでは、家族と一緒に暮らすような、なごやかな時間を過ごした。ある時、いずれ別れることになる私たちへ、アンネが涙まじりに言った。
「またトルコに来たら、この宿に泊まってね。あなたは籍を入れたばかりというから、子供が生まれたらその子も一緒に連れて来て」
 その後、アンネは「これからふたりをいいところに連れてってあげる」と私たちにささやいた。どこに行くのか分からないまま、引っ張られた先は、人がごった返す庭。そこでは、トルコ風ウェディング衣装をまとった花嫁と花婿が、沢山の人々に囲まれ顔を皺くちゃにして笑っていた。アンネは、友人のお子さんのウェディングパーティーに私達を呼んでくれたのだ。外国人は私達だけだった。
その後、アンネは「これからふたりをいいところに連れてってあげる」と私たちにささやいた。どこに行くのか分からないまま、引っ張られた先は、人がごった返す庭。そこでは、トルコ風ウェディング衣装をまとった花嫁と花婿が、沢山の人々に囲まれ顔を皺くちゃにして笑っていた。アンネは、友人のお子さんのウェディングパーティーに私達を呼んでくれたのだ。外国人は私達だけだった。
司会者に紹介され、花嫁花婿の前でお祝いの言葉とご祝儀を渡す私たち。このご祝儀がまた、日本では見たこともない、お札をネックレスにして花嫁の首に掛けるというものだった。ひと通りご祝儀終わった後は、音楽に合わせて皆でダンス。お酒の飲めないイスラム式だったが、ジュースに甘いものにご馳走にと、大騒ぎだった。
それにしても、新婚直後に飛び出したこの旅で、二度も結婚式に呼ばれるなんて、なんて偶然だろう。ふたりぼっちで始まった私たちの結婚生活に心細くもあった。だけど、文化や風習が違っても、満面の笑顔で幸せそうな皆を見て、私はどこかほっとしていた。
この旅の後、旅先で出会った人たちに感謝の気持ちくらいは伝えられるようになりたいと、言語習得を意識するようになった。そうして海外移住を決め、今は上海にいる。子供が生まれたらアンネに会わせようという約束は、日々の生活に追われて果たせないままだ。
娘は現在2歳半。インターナショナルスクールで中国語・英語に触れる毎日だ。大きくなったら自分の目で世界を感じて欲しい。年末には、ふたり目も生まれる。ふたりぼっちだった私の家族も大きくなった。アンネの家族みたいになれたかなあ。今はもう一度会って、彼女にありがとうと伝えたい。アンネ、待っててね。
三上 五月
1975年5月5日生
出身・青森県
編プロ、出版社勤務を経て、アジアを中心に放浪の旅へ。まわった国は20カ国弱。現在は上海にて子育て・主婦業に精を出す日々。第二子を身ごもりながらも、中国各地のバックパック旅行を続けている。
~上海ジャピオン8月25日発行号より




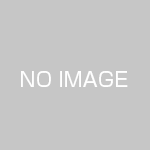












 PAGE TOP
PAGE TOP