光と影に彩られた街
発展し続ける中国において、今や最大といえる都市・上海。3000年ほど昔、西周の時代に長江が運ぶ泥によって形成した陸地だが、初めてここを〝魔都〟と呼んだのは日本の小説家・村松梢風であった。1889年、静岡の裕福な家庭に生まれた梢風は慶應義塾大学を中退した後、時代小説・伝記小説を主とした作家としてデビューする。そして1923年に上海の地を踏み、以降も度々訪れては〝通〟と呼ばれるほどに見識を深めていき、同年に『上海』を出版。これが翌24年『魔都』と改題して再版、後に中国語訳も発売された。また上海のほかにも中国各地を渡り歩き、実証に裏付けされた評伝を数多く記したことで知られた。
さて、彼が虜になった当時の上海とは、一体どんな街だったのだろうか? 23年といえば、日本の長崎港と条約によって開港した上海の日本郵船匯山碼頭を結ぶ「日華連絡船」が就航した年であり、パスポート不要で入国できたため日本だけでなく世界中から著名な文化人や芸術家が集い、華麗な多国籍文化を紡ぐ都市に変貌していった。アジアの中心にありながらヨーロッパのモダニズム文化に触れることもできる国際都市、その一方で天を貫く高層ビル群と繁盛を極める茶館、通りにはモダンな雰囲気に身を包んだ女性が佇み、裏通りを1本入ればナイトクラブやショービジネスの世界と、アヘン窟。賑やかさの裏側にのぞく危険な香りに、知識人たちがすっかり蠱惑したのも頷ける。

〝魔都〟に魅せられて
とはいえ、上海市内には1860年代から外国人が流れ込み、各国ごと居住区が置かれ、またそれが拡大し、現在も残る武康路の巴金旧居など異国情緒漂う老洋房建築が建ち始める。梢風が住んだアパートも同様だったらしく、ロシア人やドイツ人が居住していた。ここを拠点として、郭沫若や郁達夫、田漢、欧陽予倩ら、中国の若き知識人たちとの交流を通じて中国文化の奥深さ、それが内包する闇を知り、著作に認めた。
「そもそも私が上海へ行つたとにあつた.変化と刺激に富む生活を欲したからのことであつた一私の其の目的には,上海は最も適当した土地であつた」。「只、私を牽き付けるものは、人間の自由な生活である。其処には伝統が無い代りに、一切の約束が取り除かれてゐる。人間は何をしようと勝手だ。気随気儘な感情だけが生き生きと露骨にうごめいてゐる。」いずれも先に紹介した『魔都』からの一節である。人間が母国を離れて外の世界に触れようとするのは今も昔も同じだが、後段に描かれるのはもはや失われた上海の容貌だ。海外文化の流入により伝統を失っていく代わりに、思い足枷ともなり得る数々の約束事、すなわち条例や法規が事実上軽視された環境に身を置く人々は、ある種の自由を手に入れる。そしてそれを存分に享受し、気ままに暮らす様は活気に満ちあふれ、街全体が熱を帯びることにもなった。たった2カ月の短い滞在が、その後何度も彼を通わせることになったのは、作中の言葉を借りれば「歓びとも、驚きとも、悲しみとも、なんとも名状しがたい一種の感激」に取り憑かれたからだったのだろう。
梢風は帰国後、自らを熱狂の渦に巻き込んだ街へと長男夫婦を半ば強引に送り込む。しかしほどなくして長男は腸チフスで他界。長男の妻が再婚したため孫を引き取ったが、妻に任せて自身は鎌倉で余生を送った。孫である村松友視も作家となり、祖父と父の因縁の地について『上海ララバイ』など私的な作品を著した。

欧米文化への入り口
梢風が〝魔都〟上海を訪れるよりも60年ほど前、江戸時代の日本は開国を目前に、アメリカやイギリス、フランスの使節団として多くの日本人が上海へ渡った。西洋諸国への地理的な中継地点であった上海は、グローバル基準の近代的なシステムを受け入れようとする日本にとって、まさに〝入り口〟だったのである。
1962年、江戸時代の幕末長州藩士である高杉晋作は留学生として上海へと赴いた。藩士である高杉を〝文化人〟に含めたものかどうかいささかの疑念は伴うものの、ともかく彼は航海と滞在中に見聞したことを日記『遊清五録』に残した。これによれば、5月の初め、上海に到着した高杉が目にしたのは、欧米の商船や軍艦が碇泊し、陸にはヨーロッパ諸国の商社や金融業がこぞってビルを林立した外灘の風景だった。軍事技術など外国の強大なパワーを思い知らされ、列強の支配に喘ぐ姿を目の当たりにし、そこでペリー来航により開国したばかりの日本には攘夷的な動きが必要と痛感、帰国後の彼の運命を決定づけることとなった。余談だが高杉は上海でリボルバーを購入し、坂本龍馬に進呈したのだとか。
文化人の交流を促す書店
さて、この後の中国と日本は激動の時代を経るわけだが、村松と同時期的に、つまり長崎からの強いパイプが敷かれた1920〜30年代に戻ろう。この頃の日本は大正期、文明開化も一段落、といった時期だろうか。中国にも〝摩登(モダニズム)〟が定着し、ゆったりとした「旗袍」が女性の身体美を強調した「チャイナドレス」へと進化したのもこの頃である。
今でも有名な「内山書店」を興した内山完造は1913年、後の参天製薬となる「参天堂」の販売員として上海へ渡る。そして中国各地を営業するうち、中国人の勤勉さや信用を重んじる商人など庶民の文化に大きな共感を覚える。またモダニズムが進むに従い、女性の経済的自立に賛同し、妻のために四川北路の自宅に宗教書を取り扱う書店を設け、客の要望に応えて一般書の取り次ぎも始め、29年に内山書店を開いた。
ここでは森本厚吉や吉野作造などを内山が招聘し、これをきっかけに日本の文化人が多く上海を訪問、書店自体が中国と日本の文芸家および文芸愛好家の溜まり場となった。その中には田漢、郁達夫、郭沫若などの日本留学経験者である中国知識人も含まれ、中でも魯迅とは強い友情を育んだ。36年に魯迅が喘息の発作で急逝した時、その絶筆は内山へ宛てた手紙だったという。
谷崎潤一郎が訪れた際には、その著作『上海交遊記』、『上海見聞録』で書店を紹介、日本からやってくる文化人は内山書店を窓口にして中国の知識人と交流を持つのが習わしとなった。翌夏には、谷崎の紹介でやってきた佐藤春夫が中国の文学者と会うための仲介も行っている。
最貧困層を生きる日本人
前述した魯迅と親交を深めた文学者の1人に、金子光晴がいる。学生時代の金子は本ばかり読んで暮らし、ヨーロッパや老荘思想に傾倒して学業を疎かにして中退を繰り返し、あげく放蕩生活の果てに子どもを作って結婚するも、子どもは実家に預け妻を伴ってパリ行きを計画、周囲から金を借りて出かけてしまったのだった。上海には26年、花のパリを目指しながらその中継地として訪れたが、およそ40年後に発表した『どくろ杯』にてその放浪の日々を綴っている。
「今日でも上海は,漆喰と煉瓦と,赤甍の屋根とでできた,横ひろがりにひろがっただけの,なんの面白味もない街ではあるが,雑多な風俗の混淆や,世界の屑,ながれものの落ちてあつまるところとしてのやくざな魅力で衆目を寄せ,干いた赤いかさぶたのようにそれにつづいていた。」金子のこの自伝小説は非常に独特な視点で書かれており、一見して煌びやかな街の裏の顔を暴き、そこで「上海ゴロ」と呼ばれた底辺層を生きる日本人居留民の姿を浮き彫りにし、数多ある当時の上海見聞録とは一線を画したものとなった。
金子の滞在は2年に及び、彼もまた日本人の多い四川北路付近へ居を構えた。現在も四川北路1906弄にある小区「余慶坊」は『どくろ杯』に登場し、周辺の混沌とした雰囲気を如実に表している。
新聞連載の紀行文
最後に、新聞社の海外特派員として上海に赴任した芥川龍之介を紹介したい。芥川は1921年、「海外視察員」の名目で渡中し、4カ月間で上海を含む10省3直轄市を歩いた。特に北京の歴史には大いに魅了され、元朝以来の王城が置かれた街に「二三年住んでも好い」とまで言わしめた。だが愛するが故に書けない、という何とも文豪らしい理由から、北京の紀行文を残していない。やれやれ、である。
当初は現地から旅行記を書き送る約束だったが、これを果たせないばかりか帰国後も体調を崩し、翌月になってやっと紙面に『上海遊記』と『江南遊記』を連載。『上海遊記』には到着時の情景を「埠頭の外へ出たと思うと、何十人とも知れない車屋が、いきなり我々を包囲した。」とある。現在でも大きな駅で待ち受けるタクシーやツアーの客引きの強引さ、勢いの凄まじさが当時から脈々と受け継がれていることが窺える。そして最晩年、横光利一に「上海を見ておかねばいけない」と言い残し、横光はその言葉に倣って28年に上海を訪れ、新感覚派文学の集大成的長編『上海』を執筆した。
~上海ジャピオン2016年5月13日発行号










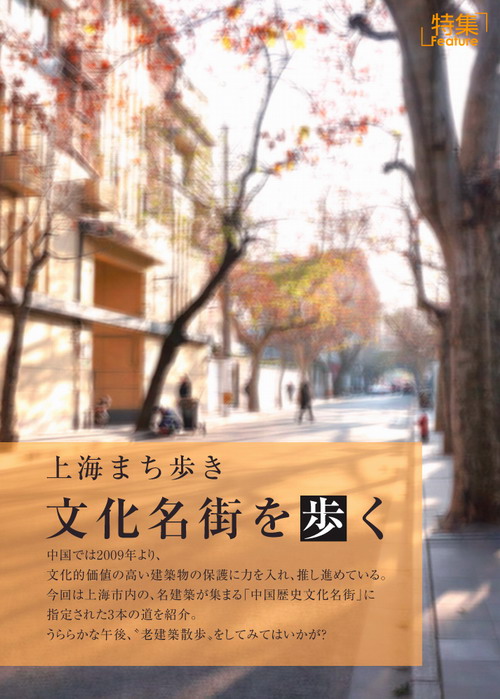










 PAGE TOP
PAGE TOP