荷物をしょって、
旅にでる。
知らなかった発見があり、
新しい人と会ったり、別れたり。
気が付くと、
忘れられない思いが残る。
旅行会社勤務、
ルポライター、
料理人、
そして主婦、
世界を旅した人たちの、
〝もう一度〟。
そんな思いを、綴ってみることにした。
ポカラのろうそく
湖に舟を浮かべ、のんびりヒマラヤを望むには絶好のロケーションにあるポカラ。山間に住む人々の心は穏やかで、土地の食材と各種スパイスを使った料理もおいしく、のんびりとした風土は、思わず沈没してしまいそうな心地よさに溢れている。1994年。インドで1カ月のフィールドワークを終え、帰国の前に1週間の予定で立ち寄ったネパール。インドの熱気とカルチャーショックにあてられ、疲れ切った私の体を、その土地は、熱を冷ましてくれるように優しく労わってくれた。
ネパールの首都カトマンズから西へ約180キロ。アンナプルナ峰を眼前に望む街・ポカラに、私の乗った長距離バスが到着すると、そこにはすでに、たくさんの宿の客引きが待ち構えていた。どこにするかは自分の勘しだい。ここは運試しとばかりに、私は、人の良さがにじみ出ていそうなウィッキーさん似のネパール人にポイントを定め、彼からこの土地に関するワンポイントレッスンを受けながら、導かれるままに宿へと向かった。
着いた先は、建てて間もない小さなゲストハウスだった。シンプルな造りの部屋で、お湯はソーラーパワーのためシャワーが数十分間しか使えなかった。
けれど、部屋には大きな窓があった。窓からはヒマラヤ・アンナプルナ峰が見渡せた。そこから望む景色だけで何もいらないと、私は感じた。その風景があれば、もうそれだけでお腹いっぱいになれると。
そんなポカラで、私はもうひとつ、一生忘れることのない風景に、出会った。
それはポカラについて2日目の夜のこと。
昼下がりから、私はペワ湖に木製の小舟を出して、アンナプルナ峰を眺めながら、のんびり読書を決めこんだ。街の喧騒からは隔離され、聞こえるのはただ水の音と鳥のさえずりだけの静寂の世界。あたかもここだけ、時が止まっているかのようだった。
ふと気づくと、眼前に聳えるヒマラヤの峰々を、夕陽はピンク色で染め上げていた。同時にゆっくりと、湖畔にある商店、レストラン、ホテル、ポカラにあるすべての建物に、やわらかい光が灯り始めたのだ。ふと昼間、宿の主人に甘いみかんをご馳走になりながら聞いた話を思いだす。
「電力不足で週に2回、決まった時間に停電があるんだよ」
街の人工的な明かりはしだいに姿を消した。代わりに、ひとつふたつと、やわらかいろうそくの灯りがゆらゆらと揺らめき始めた。あたりは暗闇に包まれ、揺らめくろうそくの灯りと、その灯りがぼんやり照らし出す街の風景とが、湖の向こう側に映し出された。湖面に倒影する光と影。幻想的な光景を前に、私は、このまま停電していてくれたらと願った……。
しばらくして、私は舟を降りた。歩きながら宿へと向かう街の風景は、昼間見たそれとは違って映った。バザール、食堂、ホテル……、すべてがおぼろげな光に包まれている。民家の窓には、ろうそくの灯りが映し出す家族の姿が、そして、街角には、静かに語りあう旅人たちの姿があった。
その夜、ポカラにいる現地人と旅行者は、やさしく揺らめく灯りの中で、穏やかに、そして静かに時を楽しんだ。彼らは、何もせず、ただ大切な人と、なんてことはない一瞬を過ごすしたのだろう。部屋の窓から、ポカラのろうそくを眺めていると、私は、そんなふうに、嫌なことも悲しいことも、すべてが、ろうそくの蒸気となってヒマラヤの高い空へと上っていくかのように感じた。
旅は、心のカンフル剤となり、私の心に刺激と感動を与えてくれる。私にとって、そのときから旅は、人生に欠かすことのできない、必要不可欠なものとなった。ほんの小さな幸せや、すぐ近くにある大切なものに気づかせてくれる旅。そんな旅の喜びを、もっとたくさんの人と分かち合いたい、そんな思いが、私を旅の仕事へと導いた。
あれから約10年。ポカラもずいぶん変わったと聞く。もう一度見たいあの風景は、もう二度とみることの出来ない風景となった。ただそれでも、時々思い出す心にやさしく揺らめく〝ポカラのろうそく〟の灯りは、いつまでも消えることなく、私の記憶の中で輝いているのだ。
福林涼子
74年生まれ、大阪出身。大学時代、初めて行った海外旅行先、タイの少数民族トレッキングでアジアにはまる。アジアと少数民族と自然好き。旅行会社、航空会社を転々とした後、3年半前上海へ。現在、日本旅行に勤務。
一瞬の死闘

七人の男が乗る小さな木船は、懸命に目の前のイルカを追いかけていた。
大きな波をかぶり、転覆しそうなほど激しく揺れるその船の後方で、私は、船にしがみつきながら、カメラが壊れることを覚悟で辛うじて片手で写真を撮るのが精一杯だった。しかし同じ船の上で、「ラマファ」と呼ばれる銛撃ちは、5メートルもあろうかという銛を両手で持ちながら、揺れなどものともせずに両足のみで舳先に立ち続けているのだ。
赤いTシャツに覆われたその背中は、「今だ!」という瞬間を待っていた。この漁は銛とともにラマファ自身も海に飛び込むという危険かつ大胆なものなのだ。
私はそのラマファの姿に驚愕しながら、目は必死に逃げるイルカの姿を追っていた。が、ふとそこから目を離して遠くを見たとき、思わず息をのんだ。強い太陽の光の下にどこまでも続く深い濃紺色の海面は、100頭以上はいようかというイルカの群れで埋め尽くされていたのだ――。
 ここは、インドネシア東部・レンバタ島のラマレラという小さな村。東ティモールの宿で知り合ったオランダ人からこの村の話を聞いて強烈に惹かれ、私はここにやってきていた。なんといっても、ラマレラでは400年前とほとんど変わらぬ方法、すなわち竹でできた銛と木造の船で、今もマッコウクジラを捕っているというのだ。私はどうしても巨大なクジラと人間が肉体同士でぶつかり合う姿が見たいと思った。
ここは、インドネシア東部・レンバタ島のラマレラという小さな村。東ティモールの宿で知り合ったオランダ人からこの村の話を聞いて強烈に惹かれ、私はここにやってきていた。なんといっても、ラマレラでは400年前とほとんど変わらぬ方法、すなわち竹でできた銛と木造の船で、今もマッコウクジラを捕っているというのだ。私はどうしても巨大なクジラと人間が肉体同士でぶつかり合う姿が見たいと思った。
レンバタ島までは、バリ島から飛行機、バス、船を乗り継いで足かけ3日。そこからさらに、非常に険しい道なき道を乗り合いトラックで4時間ほど揺られた。土埃と疲労にまみれた後に着いたラマレラは、キリスト教が根付く静かで美しい村だったが、まず目を引いたのは、人家の前にオブジェのように置かれたクジラやイルカの骨だった。
「一番幸せなときは、獲物が捕れるとき。一番辛いときは、獲物が捕れないときだ」
すでに69歳でありながら、現役のラマファとしてクジラを捕り続ける一人の男がそう言った。これ以上ないほど明快な彼のその言葉が、まさにこの村の男たちの強靭で一途な生き様を表しているように思えた。海と漁こそが彼らの人生そのものなのだ。
そんなラマレラに着いてから6日目のこと。私は彼らの「至福の瞬間」を見るために、浅黒い肌の寡黙な男たちとともに小船に乗った。そしてイルカと出会ったのだ。
100頭以上のイルカの群れ――。一瞬夢かと思うようなその光景は、まさに、リュック・ベッソンのあの「グラン・ブルー」の世界だった。光り輝く水面で飛び跳ねる無数のイルカたちは、まるで海という果てしない舞台の上で踊っているかのように見えた。しかし、自分たちはいま、そんなイルカたちに銛を撃ちこもうとしているのだ。
 私は、猛烈なスピードで逃げるイルカの大群と、船上で体を震わせる男たちを見つめながら、胸が熱くなってくるのを抑えられなかった。それはまさに「戦い」なのだ。決して技術の上にあぐらをかいた人間優位の捕獲ではなく、まさに哺乳類同士の命を懸けた真剣な戦いに違いなかった。
私は、猛烈なスピードで逃げるイルカの大群と、船上で体を震わせる男たちを見つめながら、胸が熱くなってくるのを抑えられなかった。それはまさに「戦い」なのだ。決して技術の上にあぐらをかいた人間優位の捕獲ではなく、まさに哺乳類同士の命を懸けた真剣な戦いに違いなかった。
決着の瞬間は訪れた。数頭のイルカが目の前をさっと横切ろうとした一瞬の隙に、ラマファは銛と一体となって水中に消えていった。そして船の中がわっと歓喜に沸いたとき、船から長く延びた銛綱の先では、横っ腹に銛が刺さったイルカが最後の力を振り絞るようにもがいていた……。
血のにおいに満たされた小船の中で、私は男たちの命を懸けた仕事への感動がしばらく冷めやらなかった。
心残りだったのは、ついにラマレラでクジラを見られなかったことである。巨大なマッコウクジラとの戦いこそが、彼らの本当の勝負なのだ。
そのクジラが最近捕れなくなったと嘆きつつも、男たちはただ毎日、海へ漕ぎ出していくしかない。そんな彼らとともに、いつか私ももう一度あの小船に乗り、今度こそは彼らの最高の一瞬を見てみたい。
近藤雄生
1976年7月20日生まれ。東京出身。ルポライター。
2003年より日本を離れ、オーストラリア、東南アジア、中国各地を旅しながら人物や社会に関するルポルタージュ・記事を執筆。2006年2月より上海在住。ブログ「From 2003」http://bloggers.ja.bz/ykon
~上海ジャピオン8月25日発行号より


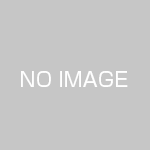












 PAGE TOP
PAGE TOP